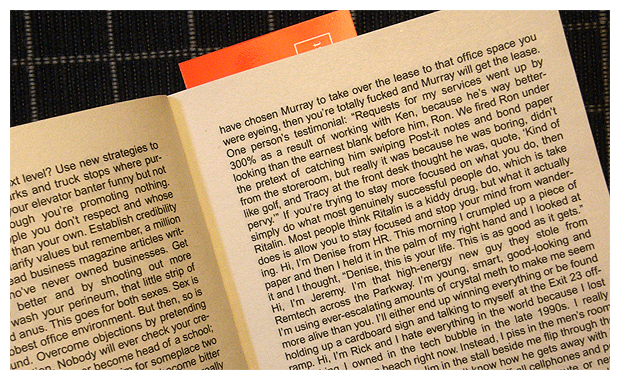「オラクル・ナイト」ポール・オースター
オースターお得意の多重構造。あとがきで柴田元幸が書いているようにオースター曰く「弦楽四重奏」な小説。
オースター自身が書く物語の中で主人公が書く物語、さらにその物語の中で。
タペストリーとかそんな上品なものじゃないけど、あやなす物語の中で人生の襞のどろりとしたものがくみあげられ、容赦なく陽のもとに晒されていく。主人公たちは、できることなら知りたくない事実をつまびらかにされ、知りたくない事実の関係性に打ちのめされる。
事実を彩るエピソードの数々。それを読む快楽。読み進まずにはいられない。
小説家の「私」シドニー・オア が、20年前(当時30代前半)に大病をした直後に起こった奇妙な出来事を書き連ねていく。
美しく、ストイックで聡明な、青い目の妻グレース、グレースの父親がわりのどこかヘミングウェイを思わせる友人作家ジョン・トラウズ 、トラウズの暴虐な息子ジェイコブ、この物語のすべての鉄爪になったポルトガル製の青いノート、そのノートを買い求めた先の文房具店主、M.R.チャン。
リアルの主要登場人物はこれだけ。
もちろんブルックリンでの物語。
「私」がポルトガル製の青いノートに万年筆で綴る物語の中で。
ニッキー(編集者)と妻イーヴァのレストランでの食事風景。ふたりはその夜、ニッキーの元にある小説を持ち込んできたローザを見かける。1927年に書かれた未発表の「オラクル・ナイト(神託の夜)」。ローザはその小説を書いた作家の孫娘だ。
イーヴァはさっきから首をのばしてローザのテーブルの方を見ている。すごく綺麗だよね、とニックは言う。でもニッキー、髪は変だし、服装は最悪よ。関係ないさ、とニックは言う。とにかく生き生きとしてるんだよ。あんなに生き生きとした人に会ったのは何ヶ月かぶりだね。あれは男をとことんひっくり返しちまうたぐいの女性だよ。
男が妻に言うべき科白ではない。特に、夫が自分から離れかけている気がしている妻に言うべき科白では。
その夜ニックは、ダシール・ハメットの「マルタの鷹」の中の登場人物をそっくりなぞったアクシデントに巻き込まれる。
「誰かが人生の蓋を外して中の仕組みを彼に見せた」ような出来事。「世界は偶然に支配されてい」て、「ランダム性が人間に、生涯一日の例外もなくつきまとって」いて、「命はいついかなる瞬間にも、何の理由もなく人から奪われうる」ことを象徴する出来事。
それは「私」が描く物語の中で主人公に与える神託。
一方「私」にとっては、ポルトガル製の青いノートこそが神託だった。
私は万年筆のキャップを外し、青いノートの1ページ目の第一行にペン先を押し付けて、書き始めた。
言葉はすばやく、滑らかに、大した努力も要求せずに出てくるように思えた。驚いたことに、手を左から右へ動かし続けている限り、次の言葉がつねにそこにいて、ペンから出るのを待っていてくれるように思えた。
オートマティズムのように書き連ねていく物語は「私」自身への神託として跳ね返っていく。
グレースの秘密と懊悩、文房具店主チャンの奸計、トラウズの息子ジェイコブの破滅、「私」とグレースを飲み込む悲劇と、トラウズによってもたらされた再生。
これより1本前の、まだ読んでいない「幻影の書」を読む前に、「幽霊たち」「鍵のかかった部屋」を再読したくなった。
January 10, 2011 in books | Permalink | Comments (2) | TrackBack